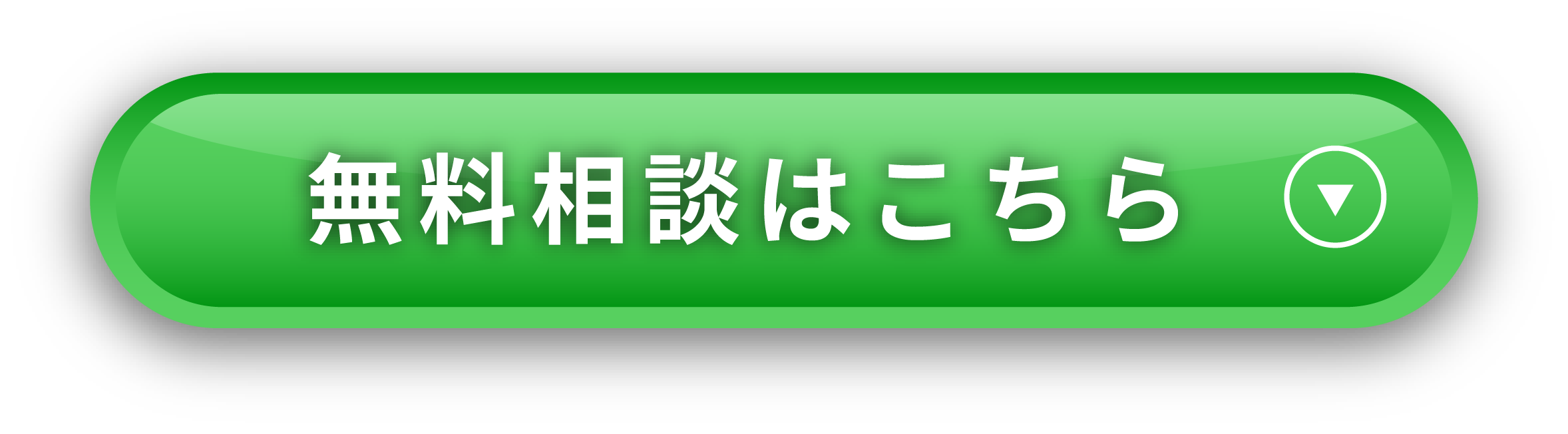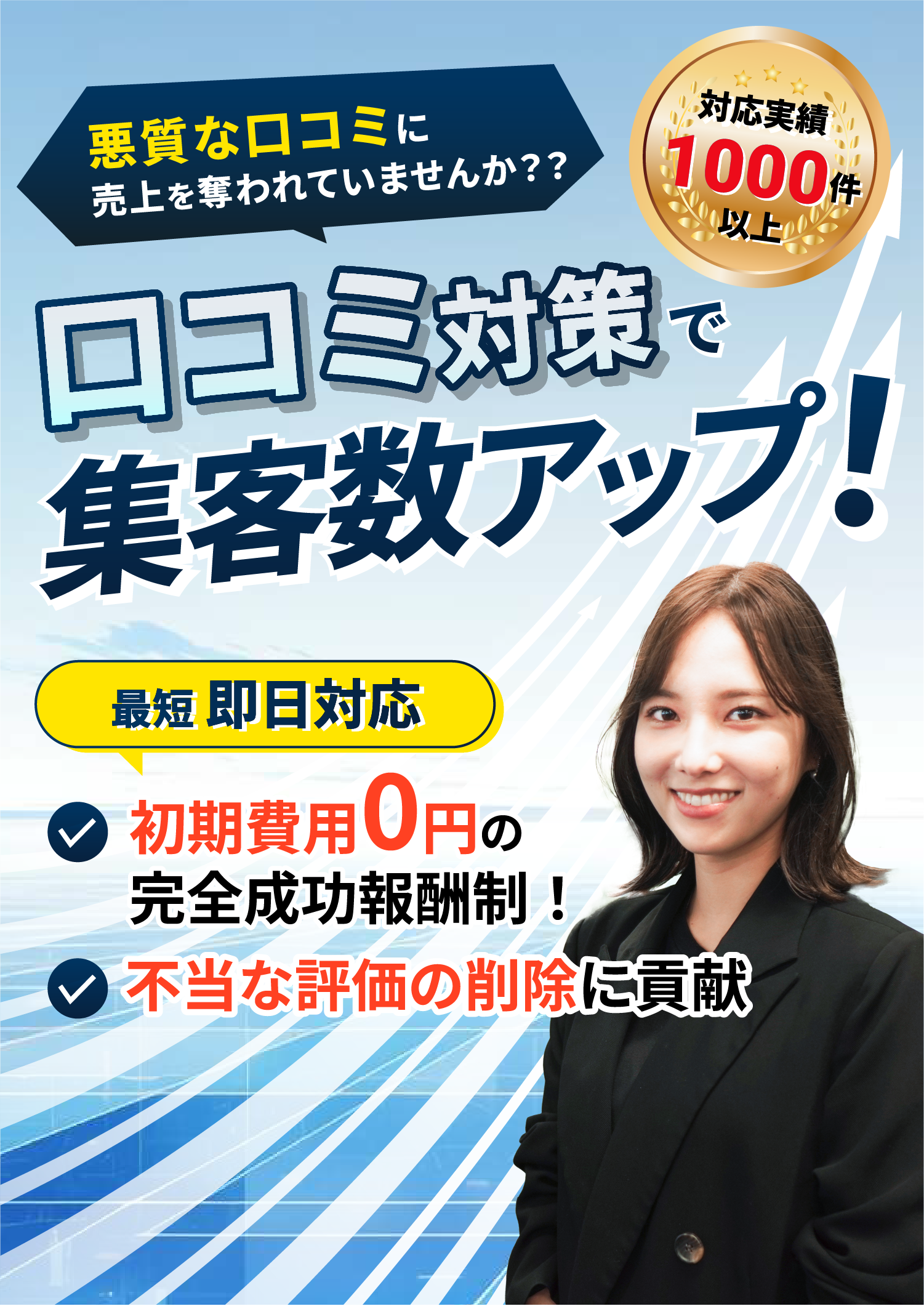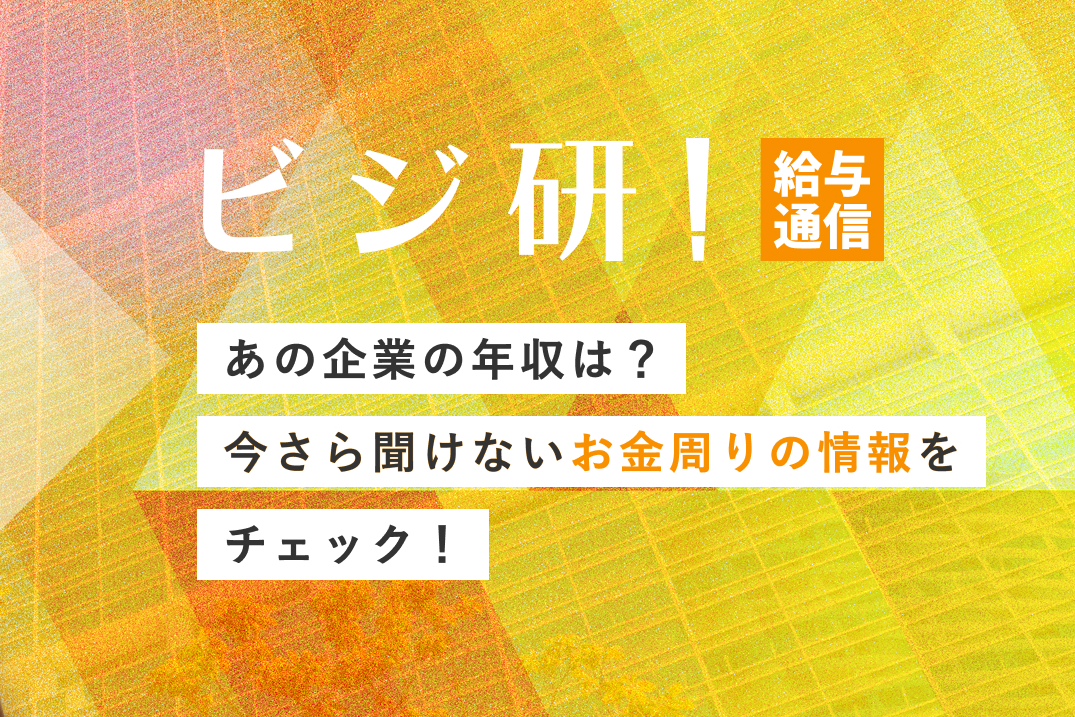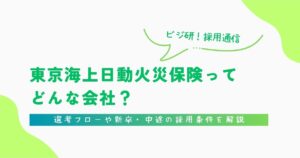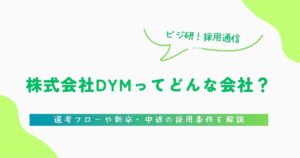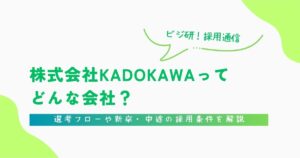【2025年度版】高収入の仕事に就きたい方必見!給料が高い仕事50選!
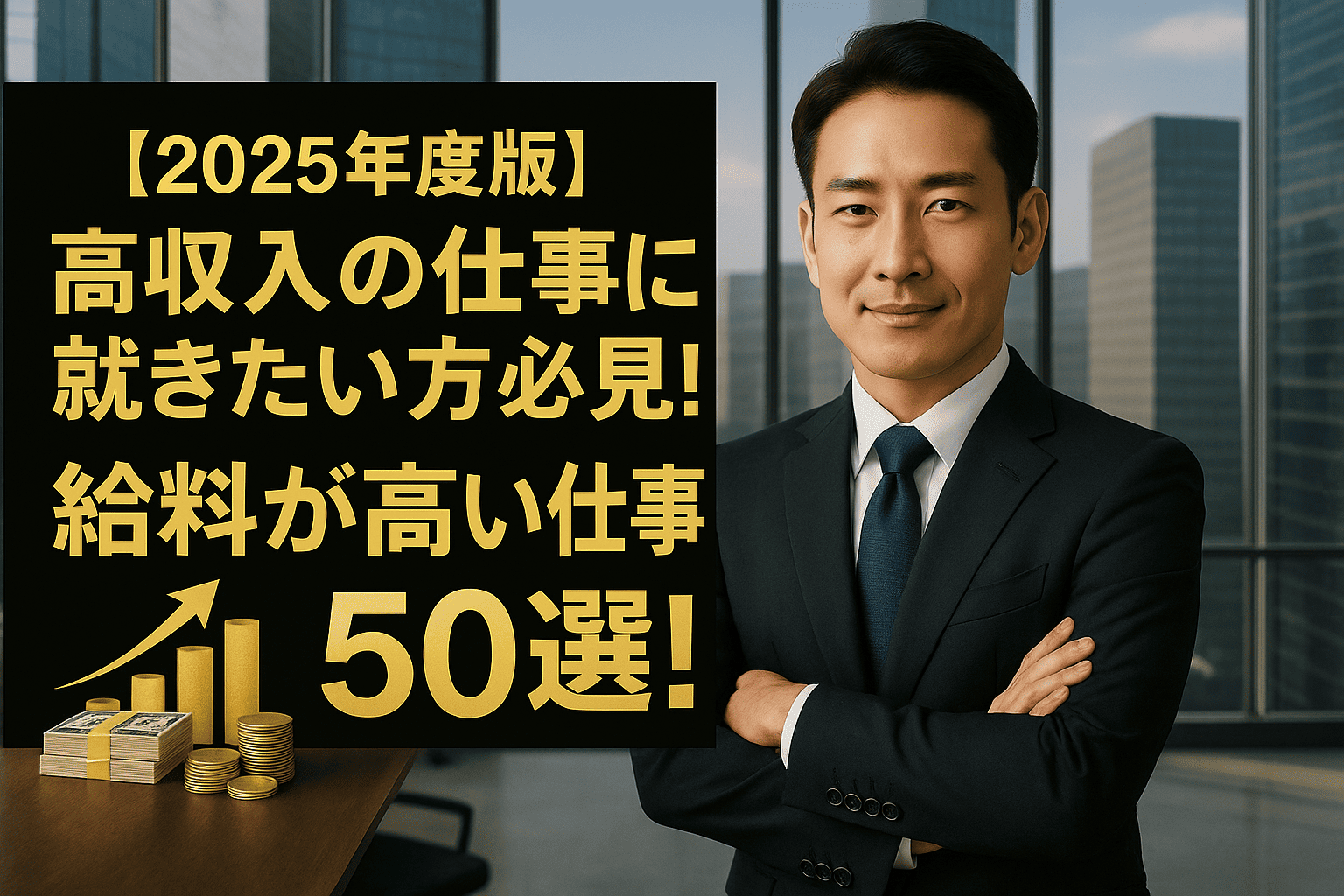

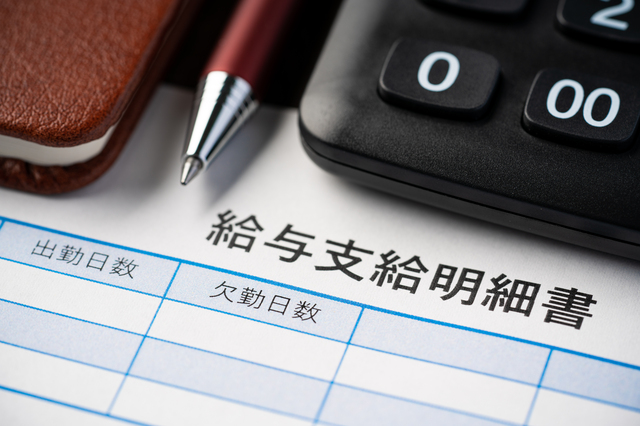
本記事では、「給料が高い仕事が知りたい!」「高収入な仕事に就くためにはどうしたらいいの?」といった疑問を持たれる就活生のみなさんを対象に、給料が高い仕事の紹介とそういった仕事に就くためのメソッドを紹介いたします。
就職活動で給料面を気にするのは、自分の人生を左右する大事な判断軸です。
ただし、給料が高いというだけで仕事を決めるのはいくつかの危険性があります。就職活動における注意点と押さえておくべきポイントも紹介いたしますので、自分に合う仕事かつ給料が高い仕事を見つけていきましょう。
「給料が高い」の基準

そもそも「給料が高い」とは、どのくらいの年収を得られる状態のことを指すのでしょうか。
年収の基準は職種だけではなく、年齢や性別、学歴によっても差が生じているのが現実です。
日本国内全体の平均年収や年齢男女別、学歴別の平均年収を基に、「高収入」といえる年収の目安をご紹介いたします。
日本国内の平均年収
(注釈)この記事でいう「平均年収」とは、以下で参照した国税庁の「民間給与実態統計調査」における平均給与のことを指します。個人の投資利益(株取引や不動産収入)は考慮されていない旨、予めご了承ください。
2024年9月に発表された国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、日本国内の平均年収は460万円でした。平成26(2014)年の平均が420万円であったことから、直近10年で40万円ほど上昇していることがわかります。
本調査の調査対象となった給与所得者の平均年齢は47.0歳となっており、平均勤続年数は12. 5年となっています。
男女年齢別平均年収
国税庁の同調査によると、男性の平均年収は569万円、女性の平均年収は316万円でした。以下の表に年齢別の平均年収をまとめました。
| 年齢 | 男性平均年収 | 女性平均年収 |
| 19歳以下 | 133万円 | 93万円 |
| 20~24歳 | 279万円 | 253万円 |
| 25~29歳 | 429万円 | 353万円 |
| 30~34歳 | 492万円 | 345万円 |
| 35~39歳 | 556万円 | 336万円 |
| 40~44歳 | 612万円 | 343万円 |
| 45~49歳 | 653万円 | 343万円 |
| 50~54歳 | 689万円 | 343万円 |
| 55~59歳 | 712万円 | 330万円 |
| 60~64歳 | 573万円 | 278万円 |
| 65~69歳 | 456万円 | 222万円 |
| 70歳以上 | 368万円 | 197万円 |
| 全体平均 | 569万円 | 316万円 |
※出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査 P.21」
男性は年齢が上がるにつれて平均年収が上がっていくのに対し、女性では平均年収が年齢に依らず一律でした。内閣府の男女共同参画局が公表している「女性の年齢階層別正規雇用比率(令和5(2023)年)」においては、女性の正規雇用比率は25〜29歳の59.1%をピークに低下しています。これは女性は結婚や出産を機に非正規雇用職員になり、結果平均年収が年齢に依らず一定になると考えられます。
学歴別平均年収
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、学歴別の平均年収は下記のようになっております。
| 最終学歴 | 男性平均年収 | 女性平均年収 |
| 高校 | 306万1,000円 | 230万5,000円 |
| 専門学校 | 325万6,000円 | 271万8,000円 |
| 高専・短大 | 354万9,000円 | 273万5,000円 |
| 大学 | 399万9,000円 | 299万2,000円 |
| 大学院 | 491万1,000円 | 407万8,000円 |
※出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
男女問わず最終学歴が上がるにつれて平均年収が高くなる傾向にあります。
「給料が高い」は年収850万円から!
給料が高いといえる基準には様々な定義がありますが、一般的には所得税の税率が最も高い区分を「高所得者」と呼ぶ場合が多いです。
以前は「年収1,000万円以上の人」が最も税率が高かったのですが、令和元年(2019年)以降は「年収850万円以上の人」が最も税率が高くなりました。
そのため、2024年現在では年収850万円以上であれば「給料が高い」といえるでしょう。
しかし、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査 P.23」では、平均年収が800万円を超える給与所得者は全体の11%と狭き門になっています。そのため、給料が高い仕事に就きたいと考えている方は、まずは日本国内の平均年収460万円を上回ることを目標にしていきましょう。
給料が高い業種ランキング
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」から、業種別の平均給与をランキング形式で下記の表にまとめました。どの業種でどれくらいの給与が見込めるのか、自分の希望業種と併せて確認しましょう。
| 順位 | 業種 | 平均年収 |
| 1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 725万円 |
| 2位 | 金融業・保険業 | 652万円 |
| 3位 | 情報通信業 | 649万円 |
| 4位 | 学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業 | 551万円 |
| 5位 | 建設業 | 548万円 |
| 6位 | 複合サービス業 | 535万円 |
| 7位 | 製造業 | 533万円 |
| 8位 | 運輸業・郵便業 | 473万円 |
| 9位 | 不動産業・物品賃貸業 | 469万円 |
| 10位 | 医療・福祉 | 404万円 |
| 11位 | 卸売業・小売業 | 387万円 |
| 12位 | サービス業 | 378万円 |
| 13位 | 農林水産・鉱業 | 333万円 |
| 14位 | 宿泊業・飲食サービス業 | 264万円 |
※出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査 P.20」
業種といっても該当する職業は幅広いため、どんな仕事をしているのか想像するのが難しい方も多いでしょう。以下に、それぞれの業種ごとに行っている業務内容について具体的に解説していきます。
1位 電気・ガス・熱供給・水道業
電気・ガス・熱供給・水道業は、社会のインフラの基盤を支える重要な役割を担う業種です。電力会社は日本各地の発電所の運営や送配電網の構築・管理を行い、ガス会社は購入した天然ガスなどから送配するガスの製造と供給を行っています。熱供給業では「地域冷暖房」と呼ばれる各地域の熱発生箇所から熱需要箇所への熱供給を行うシステムを運営し、水道業浄水場の運営や水道管の維持管理を行っています。
これらの業種は、安定供給と安全性の確保が最重要課題であり、設備の保守点検や緊急時の対応、環境への影響の考慮なども重要な業務となっております。そのための高度な技術と専門性が求められる反面、人々の生活に必要不可欠な事業のため事業としての安定性が高いです。
2位 金融業・保険業
金融業は、銀行業務、証券業務、投資顧問業務などの事業を展開し、資金の仲介や運用、決済サービスの提供などを行う業種です。主な業務として、預金の受け入れ、為替取引、投資信託の販売などがあります。保険業は、生命保険や損害保険の提供を通じてリスク管理サービスを提供する業種です。保険商品の開発・販売、保険金の支払い、資産運用などの業務を行います。
両業種とも、顧客の財務状況による需要に応じた適切なサービス提供が求められるため、金融商品や保険商品に関する高い専門性が必要な仕事です。
3位 情報通信業
情報通信業は、通信インフラの提供からソフトウェア開発、コンテンツ制作まで幅広い業務を含む業種です。通信会社やソフトウェア会社、放送局などが該当します。通信会社は通信ネットワークの構築・運営・販売を行い、ソフトウェア会社はシステム開発やアプリケーション制作などを行います。時代の最先端を担う事業が多いため、技術の進歩に適応する能力や、新しい分野・環境に興味がある人に向いている業種です。未開拓の領域に足を踏み入れられる高い専門性やスキルが求められます。
4位 学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業
学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業は、知識と技術を提供する業種です。学術研究機関では、様々な分野の研究開発を行います。専門・技術サービス業では、法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社などが該当し、専門知識を活かしたサービスを提供します。教育・学習支援業では、学校教育から社会人向けの研修まで幅広いサービスを提供します。
これらの業種では、高度な専門知識や技術の維持と向上が必須であり、それにあわせて顧客が理解を深めるために効果的な知識の伝達方法を探求していく必要があります。
5位 建設業
建設業は、建築物や土木構造物の設計・施工を行う業種です。具体的には、住宅やオフィスビルの建設、道路や橋の建設などを行います。施工管理も重要な業務の一つであり、工程管理、原価管理、品質管理、安全管理の4大管理を中心に行います。施工計画の立案や、資材や労働力の調達、施工図面の作成、現場での作業指示なども行います。近年では、環境に配慮した建設技術の開発や、ICTを活用した効率的な施工管理にも取り組んでいます。
現場での作業や企画段階で周囲の関係者と連携を多く取る必要があるため、体力やコミュニケーション能力が求められる仕事です。
6位 複合サービス事業
複合サービス事業は、複数の業種にまたがるサービスを提供する事業を指します。代表的なものでは、郵便局や農業協同組合(JA)があります。郵便局では、郵便事業に加えて、貯金・保険のサービスを一体的に提供し、JAでは、農業関連サービスに加えて、金融や保険、生活関連サービスなども提供します。
これらの事業では、多岐に渡るサービスの効率的な運営と、地域社会のニーズに応じたサービスの開発・提供が求められます。
7位 製造業
製造業は、原材料を加工して製品を生産する業種です。主な業務内容として、製品の企画・開発、原材料の調達、生産工程の管理、品質管理、出荷管理などがあります。具体的には、新製品の企画立案、生産ラインの設計と運営、製品の加工・組立、完成品の検査、梱包・出荷作業などを行います。近年では、AIやIoTを活用した生産効率の向上や、環境への影響を考慮した製造プロセスの開発にも取り組んでいます。
生産スケジュールの管理や新規開発など、企画や計画を立てて実行するのが好きな人に向いている仕事です。
8位 運輸業・郵便業
運輸業は、人や物資の輸送を担う業種です。陸運、海運、航空運輸などがあり、旅客輸送と貨物輸送があります。主な業務として、輸送計画の立案、車両や船舶、航空機の運行管理といったバックオフィス業務、貨物の集荷・配送、安全管理などがあります。郵便業は、郵便物の収集、区分、配達を行います。
両業種とも、効率的な輸送ルートの設計や、正確かつ迅速な配達が求められます。近年では、環境に配慮した輸送手段の導入や、ICTを活用した配送管理システムの開発なども行っています。
9位 不動産業・物品賃貸業
不動産業は、土地や建物の売買、物件の賃貸、管理を行う業種です。具体的には、不動産の仲介、不動産開発、ビル管理などがあります。物品賃貸業は、様々な物品を一定期間貸し出す業種で、レンタカーやリース業などが含まれます。
両業種とも、顧客のニーズに合った物件や物品の提案、契約管理、メンテナンスなどが重要な業務となっています。また、不動産市場の動向分析や、新たな賃貸サービスの開発なども行っています。
顧客のニーズを把握し適切な物件や物品を提供する営業力や交渉力が求められる仕事です。
10位 医療・福祉
医療・福祉業は、健康や生活の質を向上させるためのサービスを提供する業種です。病院や診療所はもちろん、介護施設や福祉施設なども含まれます。医師や看護師、薬剤師、理学療法士などの医療専門職をはじめとして、介護士や福祉相談員といった福祉専門職も該当します。
患者や利用者のケアが主な業務であり、高い専門知識とコミュニケーション能力が求められる仕事です。
11位 卸売業・小売業
卸売業・小売業は、商品を仕入れて販売する仕事です。卸売業はメーカーや輸入業者から商品を大量に仕入れ、小売業者や企業に販売します。小売業では、デパートやスーパー、家電量販店などの店舗で消費者に直接商品を販売します。近年ではオンライン販売の拡大に伴い、ECサイトの運営やデジタルマーケティングなども行っています。消費者のニーズを把握し、適切な商品を提供する能力が求められる仕事です。
12位 サービス業
サービス業は、個人や企業に対して様々なサービスを提供する業種です。具体的には、宿泊業、飲食業、理美容業、娯楽業、清掃業、警備業などが含まれます。主な業務内容は職種や業種によって異なりますが、顧客満足度の向上を目指したサービスの提供が共通の重要課題となっています。
また、顧客ニーズの分析や、効率的な業務運営のための仕組み作りも重要な業務となっています。
13位 農林水産・鉱業
農林水産業は、農作物の栽培、家畜の飼育、林業、漁業などを含む業種です。主な業務には、作物の栽培管理、家畜の飼育管理、森林の育成と伐採、水産物の捕獲や養殖などがあります。鉱業は、鉱物資源の採掘と加工を行います。
これらの業種では、自然環境への影響を考慮しながら、効率的かつ安定した生産や採掘を行うことが重要です。また、品質管理、環境保全、新技術の導入なども重要な業務となっています。体力や専門知識・スキル、環境への影響の深い理解が求められる仕事です。
14位 宿泊業・飲食サービス業
宿泊業は、ホテルや旅館などの宿泊施設の運営を行う業種です。具体的には、客室の管理、予約受付、接客サービス、施設の維持管理などがあります。飲食サービス業は、レストランや居酒屋などでの飲食物の提供を行う業種です。メニューの企画開発、食材の調達、調理、接客サービスなどを行います。
両業種とも、顧客満足度の向上が最重要課題であり、サービス品質の管理や、衛生管理、効率的な運営などが重要な業務となっています。お客様に満足いただくためのホスピタリティが求められる仕事です。
給料が高い職種ランキングトップ50
実際に給料が高い職種はなんなのか、厚生労働省の「令和5年 賃金構造基本統計調査」によると、年収が高い職種は以下のような順位となりました。
実際に就活されている皆さんもこちらの結果を見て、ご自身のキャリア形成の参考にしてみてください。
| 順位 | 職種 | 平均年収 |
| 1位 | 航空機操縦士 | 1779万円 |
| 2位 | 医師 | 1436万円 |
| 3位 | 法務従事者 | 1121万円 |
| 4位 | 大学教授(高専含む) | 1074万円 |
| 5位 | その他の経営・金融・保険専門職 | 947万円 |
| 6位 | 歯科医師 | 924万円 |
| 7位 | 管理的職業従事者 | 885万円 |
| 8位 | 大学准教授(高専含む) | 862万円 |
| 9位 | 公認会計士・税理士 | 746万円 |
| 10位 | 研究者 | 740万円 |
| 11位 | 輸送用機器技術者 | 712万円 |
| 12位 | 高等学校教員 | 699万円 |
| 13位 | 大学講師・助教(高専含む) | 692万円 |
| 14位 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 688万円 |
| 15位 | 獣医師 | 685万円 |
| 16位 | システムコンサルタント・設計者 | 684万円 |
| 17位 | 小・中学校教員 | 660万円 |
| 18位 | 企画事務員 | 645万円 |
| 19位 | 金融営業従事者 | 636万円 |
| 20位 | 建築技術者 | 632万円 |
| 21位 | 鉄道運転従事者 | 631万円 |
| 22位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 620万円 |
| 23位 | 機械技術者 | 612万円 |
| 24位 | その他の機械整備・修理従事者 | 605万円 |
| 25位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 605万円 |
| 26位 | 土木技術者 | 603万円 |
| 27位 | 科学技術者 | 586万円 |
| 28位 | 発電印、変電員 | 580万円 |
| 29位 | その他の営業職業従事者 | 579万円 |
| 30位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 577万円 |
| 31位 | 薬剤師 | 577万円 |
| 32位 | 金属技術者 | 577万円 |
| 33位 | 音楽家、舞台芸術家 | 573万円 |
| 34位 | 著述家、記者、編集者 | 571万円 |
| 35位 | 助産師 | 566万円 |
| 36位 | 販売類似職業従事者 | 564万円 |
| 37位 | 車掌 | 560万円 |
| 38位 | その他の情報処理・通信技術者 | 558万円 |
| 39位 | ソフトウェア作成者 | 557万円 |
| 40位 | 他に分類されない技術者 | 554万円 |
| 41位 | 製鉄・製鋼・非鉄金属精錬従事者 | 552万円 |
| 42位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 551万円 |
| 43位 | 電気工事従事者 | 550万円 |
| 44位 | 診療放射線技師 | 536万円 |
| 45位 | 航空機客室乗務員 | 533万円 |
| 46位 | 自動車営業職業従事者 | 533万円 |
| 47位 | 自動車組立従事者 | 533万円 |
| 48位 | 美術家、写真家、映像撮影者 | 521万円 |
| 49位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 516万円 |
| 50位 | その他の商品販売従事者 | 515万円 |
※出典:e-Stat「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
※平均年収=(きまって支給する現金給与額)×12+(年間賞与その他特別給与額)
以下に給料が高い職種ランキング上位10個の職業について、どんな業務内容なのか、なぜ給料が高くなっているのかを解説していきます。
これを読んで、給料が高い仕事の共通点を探ったり、自分の性格と給料が高い仕事の業務内容との相性を擦り合わせてみましょう。
1位 航空機操縦士
旅客機や貨物機の操縦、安全なフライトの計画、航空管制との連携をとることが主な業務内容となる職業です。航空操縦士は、人や莫大な費用の貨物を預かる責任が大きいため、育成コストも大きくかかります。また、長時間のフライトや時差など環境の激しい変化を伴うため、肉体的にも高負荷な仕事と言えます。以上の理由から、給料も高額となっていると考えられます。
2位 医師
来院した患者の診察、治療計画の立案と実行、外科手術や投薬の指示が主な業務内容となる仕事です。医師は、言わずもがな人の命を預かる仕事であり、少しのミスや判断の過ちで人命を落とすことにつながる仕事です。また、需要に対して医師の数が少なく、長時間労働をしなければならないため、肉体的にも精神的にも負荷が大きい職業であるため、給料が高くなっていると考えられます。
3位 法務従事者
法務従事者は、企業の契約書の作成・確認、法的リスクの評価、企業に対する訴訟の対応などを行う仕事です。専門知識が必要であり、安定した立場に立つためには弁護士の資格など高度な資格が求められることが多い職業です。企業組織のリスクを最小限にし、事前事後に莫大な損害を防ぐ役割を担うため、給料が高くなっていると考えられます。
4位 大学教授(高専含む)
大学教授(高専含む)は、大学・高専での教育活動や自身の専門分野の研究、論文執筆、学会活動などを行う仕事です。専門性が非常に高く、博士号や豊富な実績が求められます。自身の研究活動で社会や産業に貢献することに加えて、後進の育成にも相当の時間が必要となるため、給料が高くなっていると考えられます。
5位 その他の経営・金融・保険専門職
その他の経営・金融・保険専門職は、経営戦略の立案やリスク管理、投資判断などといった経営業務や、金融・保険商品の設計や販売、保険契約の査定などといった金融・保険業務を行う仕事です。大規模な資金やリスクを扱い、成功すれば高い利益が返ってくるというハイリスク・ハイリターンな業務のため、MBAやCFA資格など高度な専門知識や分析スキルが求められます。業界の競争が激しく、優秀な人材には高い報酬が支払われる職業です。
6位 歯科医師
歯科医師は、虫歯や歯周病といった歯科関連疾病の診断・治療、歯列矯正、予防歯科指導や定期検診などを行う仕事です。医師と同様に専門教育課程を修了した上で、国家私徳を取得する必要があります。そのため、元々平均給料が高くなっている上に、開業障壁が比較的低く、開業歯科医師としてさらに高い給料を見込める職種です。
7位 管理的職業従事者
管理的職業従事者は、企業や組織の管理業務や部門の目標設定と遂行、人材の採用・育成、組織全体の人事調整などを行う仕事です。給料が高い理由として、組織全体の効率や利益を向上させる役割を担うほか、成果に応じたインセンティブが支給されるケースが多いことが挙げられます。
8位 大学准教授(高専含む)
大学准教授(高専含む)は、大学教授と同様に、大学・高専での教育活動や自身の研究活動を行うほか、教授の補佐や学部運営に関する業務を行う仕事です。高度な専門性を持ち、教育と研究の両立をさせる必要がある上、将来的に教授となることを期待され、高い水準の成果を積み上げることが求められます。
9位 公認会計士・税理士
公認会計士・税理士は、会計審査、税務申告、財務の観点からの経営アドバイスといった監査・コンサルティング業務などを行う仕事です。どちらの職種も高難度な資格を取る必要があり、資格保有者自体が希少となっています。希少性が高い上、企業の財務リスクを減らし、利益に直結する業務を行うため、給料が高くなっていると考えられます。また、個人事務所やフリーランスとして働くことで、更なる収入が見込める職業です。
10位 研究者
研究者は、自身や所属する組織の研究活動を行う仕事です。大学に限らず、企業内研究者や政府機関に属する研究者などその実態は様々です。自身が携わる研究内容によって給料は左右されますが、先端技術に関わる研究者は給料が高くなる傾向があります。
給料が高い仕事の特徴
給料が高い仕事は、なんの理由もなく給料が高いわけではありません。給料が高いのにはちゃんとした理由があります。
以下に給料が高い仕事の特徴を挙げます。これらは給料が高い仕事全てで共通するわけではありませんが、自分が志望する職業とどれくらいマッチするのか照らし合わせてみましょう。
インセンティブが発生する
自分の成績が給料に反映される仕事では、もちろん自分の実力にも依りますが、高い給料を期待できます。
わかりやすい例だと、企業向けに自社製品を販売する営業職では、月ごとの自身が獲得した契約の売り上げの何%がインセンティブ(成果報酬)として毎月の基本給に上乗せされるといった企業もあります。
自分の成果が毎月の給料に反映されるわけですから、働くモチベーションを高く保ちつつ、高収入を狙うことができます。
希少性や専門性が高く知識やスキルが必要
希少性とは、需要に対して供給が間に合っていない状況を指します。
例えば、皆様にはまだ記憶に新しい新型コロナが蔓延していた時期では、新型コロナ患者に対して医療機関側の看護師や介護士が圧倒的に足りていませんでした。そこで政府は新型コロナウイルス感染症対応を行うなど一定の役割を果たす医療機関に勤務する看護士・介護士を対象に一定の給与を引き上げるといった措置をとりました。
このように希少性と専門性どちらも高い職業では給料を高くすることで、企業や政府が人材を確保しようとします。
上記のように看護資格や医師免許等では取得するのに莫大な時間がかかりますが、日頃から勉強できる語学スキルなどでも十分給料が高い仕事へと繋げることができます。
自分が興味を持てる専門分野を探して、変えがきかない人材へと成長していきましょう。
残業時間が多い場合がある
平均給料が高い職種は残業時間が多い傾向があります。というのも、例えば成果報酬型でインセンティブが発生する仕事であれば、自分の功績を残そうと規定の時間外で業務を遂行するといった社員がいるため、自ら長時間労働を選択するといったケースがあります。
また、みなし残業代が給料に上乗せされているケースもあります。これは、月に幾らかの残業時間分の残業代を基本給に加えてあらかじめ社員に与える制度のことです。みなし残業であるため、規定の残業時間程度は残業することが前提として社内に浸透している場合があります。
給料が高いだけじゃない仕事
上記では、「給料が高い業種・職種」およびそれらの業種・職種がなぜ給料が高いのかを解説してきました。
給料が高い仕事では、肉体的に負荷が大きかったり休みが少なかったりする場合が少なくありません。そこで、以下に給料が高いだけではない「肉体的に楽で給料が高い仕事」と「休みが多く取れて給料が高い仕事」を紹介します。
若いうちはバリバリ働いて効率関係なしに多く稼ぐことはできますが、定年まで20代と同じように働けるとは限りません。高い給料を保ちつつ、落ち着ける職業を探してみましょう。
肉体的に楽で給料が高い仕事
金融業・保険業
金融業・保険業は、会社や自身が担当する部署にはよりますが、基本的にはデスクワークが中心となる職業です。取引先との電話・メールのやり取りや、会社への来訪者への対応、情報管理などが主な業務内容となっています。注意点として、部署によっては外部へと営業に出向いたりする場合があるため、必ずデスクワーク中心になるとは限りません。自分が希望する部署に配属できるかをあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
取り扱う商材に対して高い専門知識を持つことを求められる仕事ですが、業界全体で需要は高く、肉体的に楽をした上で安定して高収入を狙える職業です。
情報通信業
情報通信業は、主にITを中心とした業務を行うため、肉体労働は基本的にはありません。具体的な職種として、データサイエンティストやプログラマーなどがあります。高度な専門知識や技術を求められることが多い上、業界の成長スピードが早いため常に最新の情報をアップデートし続ける必要がある職業です。
低コストで事業を立ち上げやすかったり、新たなインフラとして社会に流通しているため、需要も高く高収入が狙えます。
学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業
学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業は、デスクワークや室内作業が多いため肉体的に楽な職業と言えます。上述のとおり、これらの業種は極めて高い専門知識が求められる上、研究だけではなく教育や組織維持の業務も任されることが多いため、給料が高くなっています。
休みが多く取れて給料が高い仕事
ITエンジニア・プログラマー
ITエンジニア・プログラマーは、ソフトウェアの開発・運営、システムの設計・保護などを行う仕事です。DXが促進されている現代では需要が非常に高い上、専門知識やスキルが必要であるため給料が高い傾向にあります。リモートワークが可能であったり、IT企業の中では時代に合わせてフレックスタイム制を導入している企業が大多数であるため、柔軟な働き方が可能です。また、営業目標は特に無く、プロジェクトベースでの仕事が多く、繁忙期が過ぎると比較的自由に休みが取れるのが魅力です。
MR(医療情報担当者)
MR(医療情報担当者)は、製薬会社や医薬品メーカーの営業職として医師や薬剤師に情報提供を行う仕事です。専門性が高く、利益性が高い医療業界に属するため給料が高く、製薬会社や医薬品メーカーは福利厚生が充実していることが多く、有給取得率が高いため休みが多く取れます。
工場勤務職
工場勤務職は、文字通りの意味で工場に勤務する職業であり、製造ラインでの作業や機械の操作、製品の検品や組み立て、頻率管理・設備点検などを行います。企業や部署によっては、専門性や技術を求められることがある上、夜勤や土日出勤などがあり、それらに応じた手当が発生するため給料が高くなる傾向にあります。また、振替休日を取得できたり、完全週休二日制であったりする工場が多いため、休みも多く取れる職種です。
企画職
企画職は、新規事業の立案、商品やサービスの企画・提案を行うために市場調査や分析などを行う仕事です。会社の利益に直結する業務を担い、高い創造性や論理的思考力を求められるため給料が高い傾向があります。プロジェクト単位で業務が進むため、成果を出せれば休暇が取りやすい職業です。
翻訳家
翻訳家は、文書や音声の翻訳を行い、映像や小説の翻訳だけでなく、法律や医療など専門分野を持つ場合はそれらに特化した翻訳活動を行う職業です。高度な語学力と専門分野を掛け合わせることで、希少性が増すため給料が高く、フリーランスとして働けば自身で仕事量を調節できます。基本的にリモートワークが多いため、柔軟なスケジュールを構築でき、休みを多く取ることが可能です。
給料が高い仕事に就く方法
この記事を見ているあなたと同じように「給料が高い仕事に就きたい」と考えている人は多くいます。そのため給料が高い仕事や企業は、必然的に就職競争率が高くなってきます。
そこで以下に、給料が高い仕事に就くために取得しておいた方がいいスキルを3つ紹介します。
これら3つを備えることで、他の就活生との差別化を図りましょう。
語学スキルを磨く
近年、グローバル化が大きく進展するに伴い、語学スキルへの需要も年々高まってきています。
高性能AIによる翻訳サービスが普及しており、そういった翻訳機を使えば問題はないんじゃないかと考える方もいるかと思います。
しかし、言語はコミュニケーションの媒体であり、言葉一つで相手に与える印象が大きく左右されるのは変わらぬ事実です。そのため、企業目線では「翻訳機を上手に使える人」ではなく「言語スキルが高く、海外の方ともコミュニケーションを上手くとれる人」が望まれます。
実際に語学スキルがあるだけで優遇される、もしくは年収を挙げてもらえる企業は多く存在します。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が実施した「中小企業の海外展開に関する調査(2024年)」では、海外展開の状況について「海外展開を行っている」企業の割合は全体の 13.3%でした。「予定はある」(2.1%)、「関心は ある」(15.6%)を加えると、約3割が海外展開に何らかの関わり・関心をもっています。
大企業はもちろん、中小企業でも約3割の企業が海外展開に関心を持っているため、語学スキルを持っていることで、海外展開を実施する企業のキーパーソンに就くことができ、その仕事に見合った高い給料を得ることができます。
現在は、様々な語学スキルアップサービスが普及しているので、自分に合ったサービスを利用して語学スキルアップに繋げましょう。
必要な資格を取得する
資格を取得しておくことで、給料が高い仕事に就きやすくなります。
資格とは自分の専門知識や専門スキルの証明書であるため、志望する企業に対してわかりやすく自分の能力を伝えることができます。したがって、企業からの信頼も得やすくなり、選考で優遇されたり入社後の給与アップも見込めることができます。
以下の項目で給料が高い仕事に就くためにおすすめな資格5選を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
専門知識を身に付ける
専門知識を身につけることも重要です。
幅広い知識を持つことも重要ですが、特定の分野において深い知識を持つことで、変えが聞かない人材と認められ給料が高い仕事に就くことができます。
新卒就活において専門知識を身につけることは難しいですが、社内昇進やセカンドキャリアに向けて、入社先で日々の業務に真剣に向き合い自分の専門知識を深めていきましょう。
給料が高い仕事に就くためのおすすめ資格
給料が高い仕事に就くには、資格が必要となる場合とそうでない場合があります。以下に給料が高い仕事に就くために有利となる資格を6つ紹介いたします。
宅地建物取引士
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産業界で必須の資格であり、約6〜12ヶ月程度の学習期間で取得できるため未経験者でも取得しやすい資格です。不動産の売買や賃貸借などの仲介業務における重要事項説明や契約締結を行う際に必要となってきます。
この資格を持っていることで、営業成績に応じた歩合制でも給与上昇が期待できます。不動産業界でのキャリアアップを望むためにはあって損はなく、独立開業する際には法律上、業務には資格者が必要となってきます。
不動産関連企業では、内定承諾後に資格を取ることを求められる場合が多いため、早めに資格を取得し、他の就活生との差別化を図るにはもってこいの資格です。
ただし、宅建士は有資格者が多いため、実務経験を多く積み、交渉力や法的知識を備えていくことが重要となってきます。
一級建築士
一級建築士は、大規模建築物の建築設計や建築確認申請、建築設計事務所の独立開業を行う上で必要となる資格です。
この資格を持っていることで、二級建築士では扱えない大規模建築物の設計が可能となり、設計・デザインのプロフェッショナルとして認知され、顧客からの信頼度が高まります。そのため、商業施設、公共施設、マンション設計など大規模なプロジェクトに携わる機会が増え、高い給料を得ることが期待できます。
一級建築士は、建築物の設計や施工管理を行う際に高度な技術や専門知識が求められるため、取得するには一定の経験が必要となっており、実務経験が2年以上あることが前提とされています。試験合格には2〜3年程度の学習期間が一般的であり、合格率も10%程度であるため、決して容易に取得できる資格ではありません。その分、資格取得後のキャリアは大幅に広がっていくため、しっかり目標を立てて学習していくことが重要となってきます。
薬剤師
薬剤師は、調剤や薬の販売や指導、病院での薬剤管理業務を行う際に必要となる資格です。
医療分野では安定した需要があるため、ドラッグストアや調剤薬局、病院、製薬会社など様々な医療関連の就職先が見込めます。
上記に示したとおり、薬剤師の平均年収は577万円と比較的給料が高い職業です。加えて、医療・健康関連でありながら比較的肉体的な負担が少ないため、働きやすい職種であると言えます。管理薬剤師や独立開業など更なるキャリアアップも見込めます。
資格取得には、6年制の薬学部卒業後に国家試験合格が必要となり、しっかりと自身のキャリア形成を計画立てて実行していくことが重要となってきます。
公認会計士・税理士
公認会計士は、監査法人での会計監査業務や企業の経営企画・財務管理などの会計業務を行う際に必要となる資格です。
企業の数だけ公認会計士の需要があるため、様々なキャリア形成を実現できる職種です。一般的には、監査法人でキャリアをスタートさせ、一定の実務や経験を積んだ後にCFOや経営コンサルタントなどのキャリアアップを果たしていきます。
海外でも通用する資格であるため、グローバルな仕事をしたい方にもおすすめの資格です。
資格取得に要する学習期間は2〜4年程度で、合格率は10%程度であるため取得難易度が高い資格です。
税理士は、会計事務所や税理士事務所での税務申告業務や企業内での経理や税務管理業務を行う際に必要となる資格です。
公認会計士と同様、基本的には企業に対しての税務関連の専門サービス業務を提供する職種です。税理士事務所に就職し、中小企業や個人事業主の税務関連業務の代行などが主な業務となってきます。
税制改正が頻繁に行われるため、常に最新の情報をキャッチアップし続けることが重要です。
税理士試験は、科目合格制であり11科目中5科目を選択して合格する必要があります。科目ごとに異なりますが、資格取得のための学習期間は3〜5年程度で、合格率は10〜20%程度であるため、公認会計士同様に資格の取得難易度は高いです。
上述のとおり、厚生労働省の「令和5年 賃金構造基本統計調査」によると、公認会計士・税理士の平均年収は746万円であり、日本において給与水準が高い職種の一つです。
給料が高く安定した仕事に就き、さらにキャリアアップに繋げていきたい方におすすめの職業です。
社会保険労務士
社会保険労務士は、企業の人事・総務部門における給与計算や労務管理、社労士事務所での労働保険・社会保険手続きなどで必要となる資格です。労働法や社会保険などの労働関連の制度に関する専門家であり、企業や個人事業主に対して労務管理や社会保険の手続きなどのアドバイス・支援を行います。
社会保険労務士は、厚生労働省の「令和5年 賃金構造基本統計調査」において、「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」に区分され、その平均年収は947万円と高い給与水準を見込める職種です。
資格取得に要する学習期間は、6ヶ月〜2年程度である反面、試験合格率は6〜8%と難関な資格です。一般的には就職してから資格を取る場合が多く、日常の業務と並行して自身のキャリア形成のために隙間時間や就労後の時間を費やして勉強することが重要です。
給料が高い仕事を選ぶ上での注意点
ここまで給料が高い仕事から給料が高い仕事に就くためのノウハウを説明してきました。
しかし、「給料が高い」というだけで仕事を選んでしまったら、思わぬ落とし穴に落ちてしまう可能性もあります。
以下に、給料が高い仕事を選ぶ上での注意点をまとめましたので、仕事選びに失敗しないようリスクについてもしっかり把握しておきましょう。
肉体的・精神的にきつい
職種にもよりますが、給料が高い仕事には長時間労働が常態化しているような職種や、肉体労働やシフト勤務によって、肉体への負担が大きかったり生活習慣が乱れたりしてしまうといった労働環境である可能性があります。
また、肉体的な負担の他にも、給料が高い分、自分の仕事の責任もより大きくなるため、業務上におけるミスへのプレッシャーであったり、ノルマ達成に対するプレッシャーによって精神的負担が増えることも考慮しておく必要があります。
もちろん、体力に自信があったり、学生の頃から責任のある仕事や活動に携わってきた経験があれば問題はありません。
しかし、憧れの職業であったり、掲げている目標が高いと体や精神の負担を鑑みず、無理をして成果を上げようとしてしまいがちです。自発的にメンタルヘルスケアを行なったり、休息をとったりして自分の身体を一つの資本としてしっかりケアする自律した精神も社会人として求められます。
自分のキャパシティを客観的に見極めて、身体的・精神的に許容範囲の仕事を選びましょう。
就職難易度が高い
給料が高い仕事につける企業は人気が高いという傾向があります。そのため、優秀な応募者が殺到し、内定の席を大人数で争うことになるため、必然的に就職難易度は高くなります。
給料が高い仕事には、その職種にあった資格を持っていると優遇されたり、資格や学歴だけでなく、経験や人脈の広さを評価される場合もあるため、自分が目指す職業ではどんな人材が求められているのかしっかり分析して対策をする必要があります。
逆に、公認会計士や薬剤師など特定の資格を所有していないと募集要項を満たせないこともあるため、早めに資格を取得しておく必要があります。
このように、給料が高い仕事は内定獲得が難しく、「給料が高い」だけで仕事を絞ってしまうと内定をもらえずに就職活動の多くの時間を無駄にしてしまうという可能性があります。
入社後のミスマッチ
給料が高いことだけを重視して就職活動を終えると、入社後にミスマッチが生じてしまうリスクがあります。
企業文化や人間関係が自分に合ってなかったり、仕事が自分の思っているものとは違ったりするとストレスを感じ、せっかく入社したのにすぐにやめてしまうかもしれません。
また、給料が高いということを求人の売りにして、実際は高負荷で単調作業の繰り返しを行う仕事であったり、キャリア形成が見込みづらい職業であったりする可能性もあります。
そのため、給料だけではなく、企業文化や福利厚生、仕事内容とキャリアパスなども調べて、自分の適性に合っている仕事を探していきましょう。
仕事を選ぶ上での5つのポイント
上記で「給料が高い」だけを考慮して就職活動を続ける危険性について解説しましたが、では、就職活動をする際にどのような判断軸で仕事選びを行えば良いのでしょうか。
以下に、「給料が高い」以外に考慮すべき判断軸を紹介いたします。
これらを参考に、自分に合った仕事を見極め、充実した就職活動を行いましょう。
社風は自分に合っているか
企業文化や価値観が自分の性格や価値観と合っていないと、ストレスや不満を感じやすくなってしまいます。
例えば、大学でフットボールサークルに入会した際、自分は毎日しっかり練習してゆくゆくは大会で上位入賞を目指していきたいと考えているのに、和気藹々をモットーに週に2回しか練習がなく、部員の集まりもまちまちなサークルに入会すると、とても居心地が悪くサークル内で軋轢が生まれてしまうかと思います。
企業も同様に、社風に合っていない人材が入社してしまうと、多くの場合は企業に不利益を産んでしまい、早期退職につながる原因となってしまいます。
<社風の見極め方>
・面接時に社員に直接社風について聞いてみる
・OB/OG訪問を行う
・口コミサイトやSNSで社内の評判を調べる
やりがいは感じられるか
仕事は「お金を稼ぐ行為」に他ならないですが、仕事のやりがいを感じられないといくら給料が高くても、働くモチベーションを維持できなくなってしまう可能性があります。
志望する仕事がやりがいを感じられるかどうかは、以下の3つを元に判断していきましょう。
1.仕事の意義や目標
自分が興味を持てる分野であるのか、社会的に意義のある分野なのかどうか、あらかじめ調べておきましょう。
2.成果が実感できるものか
自分の仕事が会社やクライアントに対してどのように作用して貢献していくのかを実感できるかを調べることも重要です。また、単調な作業だけではなく自分で試行錯誤を施し工夫を凝らせる仕事であるかどうかも重要になってきます。
3.チャレンジの有無
自発的に仕事に打ち込むためには、自らの意思でチャレンジできる環境であることが前提となってきます。
<やりがいの見極め方>
・面接で社員に直接仕事のやりがいについて質問する
・業界や職種の調査を行い、自分が興味を持てる分野かどうかを確認する。
労働環境は適切か
働くモチベーションが高く保てる環境でも、労働環境が適切でない場合では、働きすぎで体調を崩してしまったり、勤務中のふとした不注意で怪我や事故につながってしまう可能性があります。
自分が志望する企業について以下の項目を必ず確認しておきましょう。
・労働時間と休日休暇制度
・福利厚生
・職場の設備
労働環境が適切に整っている企業を選ぶことにより、自らの潜在能力を発揮し高いパフォーマンスを持続的に発揮できることに繋がります。
<労働環境の見極め方>
・口コミサイトや評判を確認する
・OB/OG訪問を行う
・働き方関連のデータを見る
成長できる環境か
仕事や社内のコミュニケーションを通じて、自分が成長できるのかどうかも仕事選びにおいて重要なポイントです。成長機会が豊富な会社であれば、自分の仕事や自己成長への意欲が高まり、積極的にスキルや知識を磨くようになります。結果的に自分の市場価値が高くなりキャリアの選択肢が広がります。
自分が成長できる環境かどうかを見極めるために、以下の項目を確認しましょう。
1.ビジョンや価値観
企業のビジョンや価値観が自分の目指す方向性と一致することで、企業への貢献意識を持つことができ、結果的に日々の業務に取り組む姿勢が変わってきます。
2.研修や教育制度
言わずもがな研修や育成制度が整っている企業であるほど、社員の成長へのサポート体制が整っている企業と言えます。
3.成長事例や社員の声
自分がどう成長したいのか、合致するロールモデルが存在するのか確認することで、自分なりのマイルストーンをおくことができ、逆算的に成長していくことができます。
4.抜擢文化や挑戦できる環境が整っているか
成長意欲や実力が備わっていても、実際に責任のある仕事が任せられない環境だと自身の成長に繋げることはできません。実力主義で挑戦する若者を後押ししてくれる環境かどうかを確認しておきましょう。
自分のスキルを活かせる職種か
自分が今持っているスキルが活かせるかどうか確認するのも重要なポイントとなっています。
自分が得意とする分野や今まで培ってきた経験を活かせるポジションで働くことで、より早期に結果を出し、良い評価をもらうことができます。また、自分の能力を存分に発揮できる環境に身を置くことで、自己重要感が高まり仕事への満足度も高くなります。
<自分のスキルを活かせる職種かどうかの見極め方>
・募集要項の「求めるスキル」を確認する
・OB/OG訪問で壁打ち質問する
・企業が手がけるプロジェクトやサービスを理解する
・インターンシップに参加する
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「給料が高い仕事」について、どんな職業が給料が高いのか、給料が高い仕事の共通点や給料が高い仕事に就くためにするべきことなど、就活生の方々に役立つ情報を紹介してきました。
仕事は人生の多くを占めるライフワークです。やりがいだけではなく、今一度自分の送りたい生活水準のために必要な費用などを見直し、求める給料の基準を設けてみましょう。
本記事が、より有意義な社会人生活を送るための一助となれたら幸いです。

 お問合せはこちら
お問合せはこちら